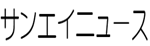
東京三栄会 文化交流委員会主催 「第 1 回東京のスリバチを歩く会」開催
東京三栄会 文化交流委員会では、2025 年 4 月 12 日(土)に街歩きイベントの新企画として、東京スリバチ学会の皆川会長をお招きし、「第 1 回 東京のスリバチを歩く会~四ツ谷は四つの谷でできている~」を開催しました。
東京スリバチ学会の皆川会長は、就職して上京した際に、谷や坂の多い東京の地形に魅了され、2003 年に「東京スリバチ学会」を設立しました。谷と坂が織りなす、東京のすり鉢状の地形を歩いて、観察して、その成り立ちや文化についてユルく、楽しく、街を愛していこうという団体で、会員規約も入会資格もありません。テレビでおなじみのタモリさんも地形が大好きで「タモリ倶楽部」や「ブラタモリ」に複数回、出演された経歴の持ち主。現在も大手建設会社に勤務するかたわら、スケジュールを空けて頂き、東京三栄会 文化交流委員会のために案内をして下さいました。今回は、スリバチ地形が最も分かりやすいという四ツ谷のスリバチ地形を観察して歩きます。

JR 中央総武線各駅停車の信濃町駅の改札前に集合して、スリバチ地形を観察して歩く「スリバチ歩き」がスタート。駅から歩いてほどなく、道の下にスリバチ地形を発見。
坂を下っていくと、千日谷がありました。もとはこの場所に一行院というお寺があり、千日谷になったとのこと。今では住宅街になっていますが、川があった場所が道になっていて、港区と新宿区が接し、「こんなに区の境目が入り組んでいる場所を初めて見た。」との声も。道端には消防用の井戸もあり、かつての名残を感じさせます。


次に立ち寄ったのは「せきとめ稲荷」という小さな祠で、かつてこの場所に川を堰き止めた「洗い場」が設けられていたとのこと。この場所は、千日谷と鮫ヶ橋谷の合流地点で古くから洪水が起きやすいため、現在も公園の下には、大きな貯水池があります。



「せきとめ稲荷」の次は、鐙ヶ淵跡(あぶみがふち)です。ここは源義家が馬の鐙(あぶみ)を落としたとの伝説が伝えられています。この辺りにはたくさんの寺院がありますが、江戸時代に江戸城の外堀や四谷門の築造に伴い、周辺のお寺が強制的に移転させ られ、谷底に集められたという歴史的な経緯があります。

鐙ヶ淵跡をあとにして、若葉公園に到着。都心の住宅街の中にある公園ですが、片隅では、わき水が湧いていました。若葉公園の南側の丘を越えると別のくぼ地があり、とても急峻です。江戸時代に高台は武家屋敷、谷底は庶民の小さい民家が密集していた歴史 があり、今でも高台は土地の区割りが大きく、ビルや豪邸が建ち、谷底は小さな民家が建ち並んでいます。

若葉公園の北側のくぼ地の谷頭にある須賀神社にて、小休止。この神社は、アニメ映画「君の名は。」のモデルになった神社で、急な階段をバックに映画の一場面を再現するインバウンドの外国人旅行客の姿がありました。

最後に荒木町の谷の観察です。この谷には江戸時代に、わき水により4mもの滝がながれ、当時構築されたダムによりせき止められていました。そこに人工池を作り、美濃国高須藩主 松平摂津守の大名屋敷の庭園とした歴史があります。その後、主を失って荒れ果てた時期もありましたが、滝の周りに茶屋や芝居小屋が集まり始め、花街として発展してきました。そんな歴史あるダムの上も、今ではマンションが建ち、解説を聞かないと通り過ぎてしまう日常の街の風景が広がっていました。そして谷底の「策(むち)の池」を観察。この池は、徳川家康が鷹狩の帰り道に策(むち)を洗ったと言い伝えられ、畔には津の守弁財天の祠があり、水辺の憩いの場として地域の方々により手入れがされています。


約3時間のスリバチ歩きは四ツ谷の坂を上り下りして、地形の奥深さと歴史や文化を学びながら、東京のスリバチ地形を体で感じる街歩きでした。終了後は、皆川さんを囲んでの懇親会があり、ブラタモリのロケの様子や裏話、段差がたった 30cm の「上級者向けスリバチ地形」の話、海外のスリバチ地形の話などで盛り上がりました。今年の晩秋から初冬の頃、これまで継続して開催してきました街歩きの会を開催予定です。こちらもぜひご参加ください。

(三井物産ビジネスパートナーズ(株) 新井貴裕)