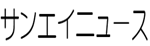
東京三栄会 文化交流委員会主催「第9回街歩きを楽しむ会」開催
東京三栄会 文化交流委員会では、2024年12月1日(日)に「年の瀬の深川と隅田川の風景を歩く」と題して、第9回目となる街歩きを楽しむ会を開催しました。当日は計8社より 12人が参加し、地下鉄門前仲町駅に集合。ガイドさんは、今回も TOKYO 歩っく!を主宰されている鎌田さんです。当日は暖かな小春日和で街歩きにはぴったりな天候で、階段を上り辰巳新道から街歩きをスタートしました。

TOKYO 歩っく!のホームページもぜひご覧ください
TOKYO 歩るっく! | まち歩きの達人のプライベート散歩会

この界隈は、終戦後、GHQ の指令により居酒屋や小料理店を一か所に集めたことがきっかけになってできた場所とのこと。横丁のオツな雰囲気に「今度、飲みに来てみたいね。」と言う参加者の声も。
進んでいくと「深川公園」がありました。今では何の変哲もない普通の公園ですが、江戸時代には「永代寺」という富岡八幡宮の別当寺があり、明治時代の廃仏毀釈により廃寺に。その跡地を利用して、明治6年に日本最初の公園のひとつとして開園したそうです。

次に深川不動堂を見学。屋台も出ていて年末の雰囲気で、少し歩いた先には富岡八幡宮がありました。この富岡八幡宮は「江戸勧進相撲」発祥の地であり、新横綱が誕生すると境内の石碑に刻名が行われ、新横綱の土俵入りが奉納されるなど、相撲と縁の深い神社です。

緑色の屋根は成田山新勝寺の深川不動堂。少し歩いて道路を渡ると富岡八幡宮です。

富岡八幡宮境内には、歴代横綱の名前を彫った大きな石碑と高さ4m、重さ 4.4t の日本一の大神輿があります。
富岡八幡宮の境内を抜け、住宅が立ち並ぶ静かな道を歩いていくと、寛永6年(1629年)に創建された正源寺に到着しました。このお寺の境内には「判じ絵」といって江戸時代の町人の間で流行した絵によるなぞなぞが掲示されています。街歩きの一行が謎解きに挑戦していると、たまたま住職がいて、これから掲示する12月分の判じ絵を見せてくれました。

歩いている途中にあった「やきとり 庄助」はテレビ番組「孤独のグルメ」の第一回目のロケ地。
正源寺を出発して、のんびりと歩きながら、次は「於岩稲荷」(おいわいなり)にお参り。この稲荷神社は、元々四ツ谷にあった神社で、江戸時代に歌舞伎役者・市川左団次が、自分の私有地であった新川に移動させたもの。ちなみに、四ツ谷怪談の「お岩さん」は有名な話ですが、元々は単なる「仲の良い夫婦」であったお岩さんの話を、江戸時代に怪談仕立てにしたもので、元々のお岩さんは怪談と関係ないそうです。

道を進んでいくと、銀色に光るきれいなトラス橋がありました。この「南高橋」は、元は両国橋として明治 37 年(1904 年)に作られたのち、関東大震災の復興事業によって両国橋を現在のものに架け替えた際、損害の少なかった部分を再利用して架橋したそうです。車が通れる現役の鉄橋としては、都内で最古のものです。

青空の下で銀色に輝く橋は、写真で見るよりとてもきれいでした。
南高橋を渡ってしばらく行くと、鉄砲洲稲荷神社がありました。平安時代創建と言い伝えられるこの神社には、「富士塚」があり、あの広重の浮世絵「名所百景」にも描かれています。ちなみに、境内では年明けに仮設のプールを設置して「水行(寒中水泳大会)」が行われるとのこと。

後日、年明けの成人の日に行われた「寒中水泳大会」を見に行きましたら、迫力満点でした。
ランチ前の午前の部の最後は、築地教会を敷地外から見学しました。キリシタン禁制が解かれた翌年の明治7年に東京で初のカトリック教会として建てられたもので、初代の建物は関東大震災で倒壊してしまったため、昭和2年に再建されました。現在では、中央区の文化財に指定されています。

築地教会の近くのホテル京阪 築地銀座 グランデで、いよいよお待ちかねのランチタイムです。メニューはミックスフライとミニバイキング。ミニバイキングではサラダの他にお味噌汁やスープ、デザートまであって、「どれを食べるかとっても迷う・・・」という声が聞かれるほど。ホテルの素敵な雰囲気の中、自己紹介の後に午前中の街歩きの感想などで交流し大いに盛り上がり、休憩時間の1時間はあっという間でした。

午後の部の最初の訪問場所は、築地の本願寺です。日本では珍しいインド風の立派なお堂がとても印象的で、階段の手すりには様々な動物のモチーフが飾られていました。一番上には鳥が飾られていて、これは「物事は全体を見渡すことが大事」という説話に基づいて配置されたものと言われています。

1998 年に急逝した X Japan の hide さんの葬儀が営まれたのもこの本願寺で、本堂1階には hide さんを偲ぶコーナーが設けられ、今でも全国のファンからメッセージやグッズなどが寄せられている様子に胸が熱くなりました。
本願寺を後にして、隅田川にかかる「勝鬨橋(かちどきばし)」を歩いていると、橋の中に事務所のような小屋と、小さな信号機がありました。勝鬨橋は大きな船が通れるように橋の中央が跳ね上がる「可動橋」で、1960年代半ばまでは実際に跳ね上げられて、動いていました。その後、観光のために再度、動かす構想もあったようですが、電気が通っておらず、修理・改修等も必要なことから動かせないまま現在に至ります。歩いてみると、元は可動橋だったため、車が通ると上下に揺れが激しいことが分かります。

中央部分が跳ね上げられている間は、歩行者も渡ることができないので小さな信号機があります。 白黒の写真は跳開している勝鬨橋(1961 年頃)
勝鬨橋を渡ると、タワーマンションが立ち並ぶ豊洲の街歩きです。深川の歴史的な風景と違って、未来的な新しい街並みがありました。途中には、2021 年の東京オリンピックの選手村だったタワーマンション(現在の“HARUMI FLAG”)もあり、大会開催時の運営に会社として協力した際の思い出や、当時の選手村の様子を話してくれた参加者もありました。

周辺には、都営大江戸線の勝どき駅しかなく、朝はタワーマンションから出勤する人でとても混雑する為、道に右側通行のお願いの看板があります
豊洲のタワーマンションの街並みを抜けると、晴海運河を渡る新しい橋、豊洲大橋がありました。この豊洲大橋は都心のビル群や東京タワーやお台場のレインボーブリッジが良く見えて、とっても良い景色。途中に4か所も展望スペースが設置されています。

豊洲大橋を渡ると、いよいよ今回の街歩きのゴール、豊洲市場の「千客万来」です。開業まで紆余曲折あったのはご案内の通りですが、日曜日の午後と言うこともあり、大変な賑わいでした。「千客万来」の屋上は、無料で楽しめる足湯コーナーがあり、仕事上がりにのんびり都心の夜景を眺めながら、寄り道はいかがでしょうか。

そして鎌田さんの計らいで豊洲市場の屋上に行ってみると、誰もいない静かな緑地広場になっていて、落ち着いて都心の風景が楽しめる「知る人ぞ知る」絶景スポットでした。

豊洲市場の屋上の緑地広場では、お掃除ロボットのような芝刈り機が、1 台で黙々と広場の掃除をしていました。

そして16時になり、ゆりかもめの市場前駅で解散です。1万2千歩を超えるロングコースでしたが、歴史を感じられる深川と、未来的な街並みが広がる豊洲を歩いて楽しい一日になりました。この街歩きに触発されて、さらに 1.4 キロほど歩いて豊洲駅から帰宅した参加者もあったほど好評を頂き、これからも継続して開催してまいります。

(文化交流委員 三井物産ビジネスパートナーズ(株)新井貴裕)